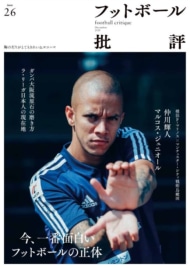ペップと一線を画すポステコグルーの偽SBへの高い依存度
偽SBに特徴を持つ両チームが相まみえたのが今年の7月27日、日産スタジアムで行われたユーロジャパンカップだ。試合前の会見でペップは「シティとF・マリノスは似た哲学を持っている。両チームともにボールを持って攻撃するプレーを好む。そして得点を望んでいる。その実現こそが、フットボールの素晴らしさだ」と語った。
この試合でシティが偽SBを活用するシーンはそれほど多くなかった。その代わりに見せたのが、横幅を大きく使った攻撃だ。
ペップはバルセロナ時代から一貫して、WGに広く張ったポジションを取らせることが多い。敵の守備ブロックを横に広げることで空くギャップを突くためだ。
バイエルン・ミュンヘンの監督に就任してからはWGの突破力やクロス、レヴァンドフスキの得点能力を活かすために偽SBを披露。シティではその偽SBを活かしてさらに敵の守備陣を縦に間延びさせつつ、チャンネル(“チャンネル”とは相手CBとSBの間にあるスペースのことを指す。そのスペースにインサイドハーフなどが入り込んでゴールを襲う)を攻略する段階まで進化させた。
彼の強みは敵、味方、試合の状況に応じて采配を変化させることができる点にもある。偽SBを行わせる必要がなければ無理にその策を取らず、最終目標である勝利のための最善策をとる。
対してポステコグルーは偽SBへの依存度が高い。
オーストラリア代表監督時代、優勝を飾った2015年アジアカップではアンカーを置く4-3-3、Jリーグ入り直前までは3バックを採用していた。しかしどちらもボール保持の意識は高いものの、ポジションチェンジによる揺さぶりはほとんど見られなかった。
ボールを受けたWGが、オーバーラップを仕掛けるSBへと繋いでクロスを上げるという攻撃に終始するものの、リスクをかけない攻撃であるためカウンターを受けても人数がそろっているという、今とは正反対のサッカーを展開していたのだ。
(文:とんとん)